被相続人の相続対策とは
- ホーム
- 被相続人の相続対策とは
認知症に備える相続と資産管理の対策
2022年時点で65歳以上の人口が29%と超高齢社会に入った日本では、認知症対策の重要性が増しています。認知症が進行すると財産管理ができなくなるため、さまざまな法的制約を受けます。とくに不動産取引において贈与・遺言作成など、重要な決定が無効となる可能性があり、相続対策の選択肢も少なくなります。
認知症発症前に財産を把握し、生前贈与や遺言書作成など、適切な相続対策を講じる必要があります。不動産アカデミア株式会社では、経験豊富な不動産のプロが、大切な資産を守るお手伝いを全力で行います。どうぞお気軽にご相談ください。
認知症発症前の対策

将来に備える重要性を考えると、遺言書作成や生前贈与などの相続対策に加えて、家族信託などが有効な選択肢となります。また任意後見制度を利用することで、信頼できる人を後見人に指名できます。
家族信託とは
家族信託とは親族間などの当事者間の合意に基づく契約を交わし、資産の運用や管理を委託する仕組みです。
家族信託を利用する方法
以下の手順を踏むことで、家族信託を利用できます。
- 信頼できる家族間で信託契約を締結
- 信託専用銀行口座を開設
- 不動産の場合は信託登記
ただし、信託財産に不動産が含まれる場合、固定資産税評価額の0.4%に相当する登録免許税が発生します。
相続「する側」の方に生前対策が必要な理由

相続のトラブルを回避するには、生前に以下のような対策をしておくことが重要です。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 生前対策の種類 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 親族間の争い対策 | 財産継承の方針決定のための遺言作成や親族間の話し合い |
| 納税資金対策 | 不動産の売却や生命保険の活用 |
| 相続税対策 | 生前贈与や資産評価の見直し及び財産の正確な把握 |
対策をしておかないと相続税が増えることになり、結果的に相続人の負担となります。
生前対策における不動産贈与のメリット
生前対策のなかでも、不動産の贈与は特に重要です。不動産の生前贈与には、以下のような4つの重要なメリットがあります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 生前贈与のメリット | 具体例 |
|---|---|
| 特例を活用することで贈与税を抑えられる | 例えば、「相続時精算課税制度」を活用すると、2,500万円まで非課税で贈与可能(超過分には一律20%の贈与税が適用)。また、「住宅取得資金の贈与の特例」を利用すると、一定の要件を満たせば最大1,000万円(2024年)まで非課税。 |
| 贈与相手を自由に選択可能 | 複数の子供がいる場合、相続争いを避けるためもっとも面倒を見てくれている長女に実家を贈与できる |
| 贈与時期を自由に選択可能 | 子供が家を購入する購入資金として自宅の一部を贈与したり、孫の教育資金として不動産を贈与したりできる |
| 不動産所得を受贈者へ移転可能 | 賃貸マンションを子供に贈与することで、親の所得税負担が軽減され、賃料収入で子供の生活支援ができる |
上記のように不動産の生前贈与は、将来を見越した賢明な選択と言えます。
相続の生前対策

相続に関する問題を事前に解決し、円滑な資産承継を実現するためには、生前対策が重要です。ここでは以下の3つの観点から、生前対策を講じる目的を説明します。
遺産分割の対策
相続に関するトラブルの中で最も多いのは、遺産分割をめぐる問題です。中でも不動産の分割は均等に分けることが難しいため、家族間の紛争に発展するケースもあります。
トラブル回避には、遺言書の作成が有効です。事前に協議のうえで財産分配方法を決めることで、相続トラブルを防いで関係者全員が納得できる形で相続の準備ができます。
相続税の対策
財産の分割方法が決まれば、各相続人の相続税額が算出できます。相続税は通常、相続を知った日の翌日から10か月以内に納付が必要です。事前に「納税するのに十分な現金があるか」を確認し、不足時の調達方法などを検討しておきましょう。
二次相続の対策
相続は段階的に発生することがあります。例えば、父親の死亡による「一次相続」の後、その遺産を相続した母親の死亡で「二次相続」が発生するケースです。二次相続では主に以下のようなデメリットが発生します。
- 配偶者控除が使えなくなる
- 基礎控除額が減る
- 相続税額が増える
- 相続人間でトラブルが起こりやすい
このような点から、二次相続まで考慮した相続対策をおすすめします。
生前贈与について
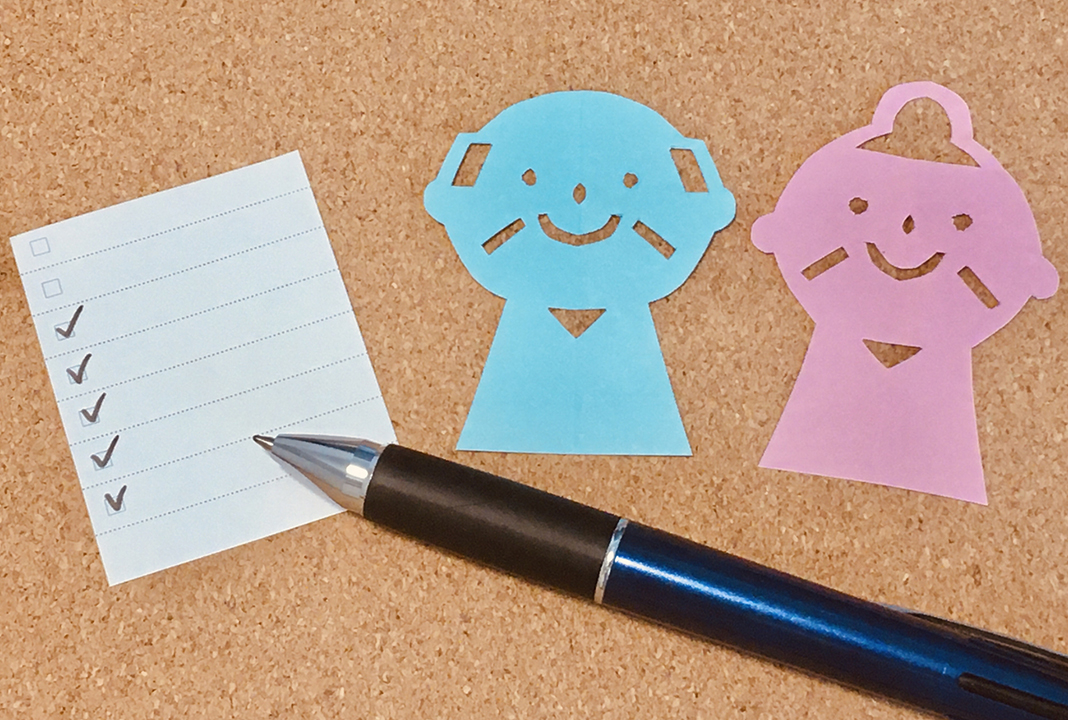
生前贈与とは、相続人となる人に対して、被相続人が生きている間に財産を譲渡することです。生前贈与をおすすめするのは、以下のようなケースです。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 生前贈与をおすすめするケース | 理由 |
|---|---|
| 資産価値上昇が 見込まれる財産の早期贈与 |
贈与時の評価額で税金が決まるため将来の値上がりを見越して早めの贈与が有利 |
| 65歳以上の親から18歳以上の子への贈与 | 相続時精算課税制度の活用が可能。この制度では、特別控除額(限度額2,500万円)が適用され、2,500万円まで贈与税がかからない。超過分には一律20%の贈与税が課税されるが、将来の相続時にすでに納めた贈与税分が控除される |
遺言書について

遺言書とは、死後の財産分配や諸事項について所有者自らの意思を書面で残した法的文書です。遺言書の有無は相続のあり方に大きな影響を与えます。遺言書がない場合、法定相続分に基づいて財産が分配されます。一方で遺言書がある場合は「全財産を妻に相続させる」「長男には不動産を次男には会社の株を相続させる」「あしなが育英会に1,000万円寄付する」など、その内容に従って分割が行われるからです。
正式な遺言書があれば、不動産相続登記の手続きの簡略化や相続争いのリスクを抑制ができます。しかし、遺留分を侵害するような内容は相続人間でのトラブルになりかねないため、相続予定者全員へ事前説明を行い合意を得ておくことが大切です。
不動産の相続登記に使える遺言書とは?
不動産相続登記に有効な遺言書は、以下の3種類です。
- 自筆証書遺言:家庭裁判所での検認が必要(遺言書保管制度を利用した場合は検認不要)
- 公正証書遺言:公証役場で作成するため検認は不要
- 秘密証書遺言:家庭裁判所での検認が必要
検認とは、家庭裁判所が遺言書の真正性を確認する手続きです。遺言を残す際は、上記いずれかの正式な形式を選択することが重要になります。
財産の把握

財産を把握することの重要性
多くの人は親の財産状況を把握していません。しかし、緊急時や相続時に財産情報が不明だと、相続財産の把握や相続人の特定から始めなければならず、相続人の負担が増大します。
トラブル回避のためにも、親子間で財産や相続について話し合っておくことをおすすめします。
把握しておきたい財産のリスト
相続時のトラブルを未然に防ぐため、以下の財産を把握しておきましょう。
- 不動産(土地、建物)の所在地と評価額
- 預貯金の金融機関名、口座番号、残高
- 有価証券(株式、投資信託など)の種類と評価額
- 生命保険の契約内容と受取人名義
- 貴金属、美術品などの資産と評価額
- 負債(住宅ローンなど)の残高
- 遺言書の有無と保管場所
- 相続に関する契約書(生前贈与契約など)
- 不動産の権利証(登記済証、登記識別情報)
相続でお悩みがあれば、不動産アカデミア株式会社へお気軽にご相談ください。不動産の相続に詳しい経験豊富なスタッフが、ご状況やニーズに合わせて丁寧なアドバイスを行い、万全の体制でサポートいたします。

